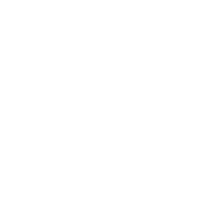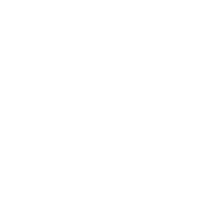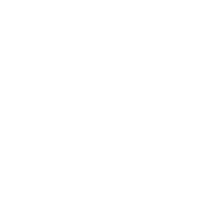今回も最初の一音から、最後の一音が消えるまで、音楽に満ち溢れた横山幸雄ワールドを堪能することができました。
演奏会を振り返っているうちに、音楽の正体、聴き方について私が大好きな指揮者チェリビダッケの言葉を思い出しました。
以下、拙いまとまりのない長文となりましたが、ご一読いただければ幸いです。
私(弊社代表取締役 渡辺)は音楽を専門に学んだことなどはありません。
また、楽器もほとんど演奏したことはありません。
ひたすら“聴く”ことだけ、それも特定のオーケストラ、特定の指揮者中心のクラシックファンでした。
それでも、演奏をどのように楽しんだらよいのかと、白水社から刊行されていた吉田秀和全集などを購入して読んだり、その影響から、楽譜と照らし合わせながら聴いたりしたこともあります。
しかし、そんなことをしているうちに、そうした分析的、批評的な聴き方はどこかまちがっているような気がして、自然に、「知性でもなく、感情でもなく、耳ですらなく、“意識で聴く・身体で聴く”」というようなやり方になっていったような気がします。
そもそも、音楽を聴いているのは誰かといえば、他でもない“わたし”自身です。
わたしが満足すれば――すなわち“わたし”が満たされれば――それでよいはずです。
私の内なる“わたし”という真我と、“いまここ”に現れている音楽との共鳴、共振(チェリビダッケの言う“響き”に近いもの)、それによる調和と安らぎ、癒し、私が音楽に求めているものはそんなものといえます。
換言すれば、音楽による瞑想を試みているのかも知れません。
音楽に対するこのような観念や姿勢は(後で知ったのですが)指揮者チェリビダッケに似たところがあったようです。
しかし、高校生の頃から始まったクラシック音楽に対する私の姿勢はずっとそんなもので、チェリビダッケを知る以前からずっと一貫しています。

ですので、チェリビダッケの以下のような言葉は、とてもしっくりときます。
「音楽の定義などできない。それは思考の範囲を超えたところにある」
「音楽を理解などできない――それは体験されるものだ」
「あなた方はみんな音符屋だ。ところが音楽は音符とはまったく関係ない!
音符はモノを入れて運ぶ器である。その中身が音楽なのだ」
「音楽が美しいと思うのは勘違い、それは真実の啓示なのだ」
「あなたが音楽で美しいものを体験しようとしても無理である。音楽では真実が問題なのだ。美は擬似餌にすぎない」
「これ以外にはありえないなにかを“体験すること”、いいかえれば、真理にふれること、人生や世界、あるいは宇宙の真相を垣間見ること、これこそが藝術なのだ」
弊社が出版している『ディヴァインヒーリング』という書物にはさらにシンプルに「音楽は神の愛であり、英知である」とされています。
このような認識は私にぴったりとしています。
しかし、実際に聴く音楽や演奏スタイルの好みに関しては、チェリビダッケと正反対のこともあり面白いもの、というよりも、人間も音楽も、そうした尺度を超えた多様な存在なのでしょう。
たとえばチェリビダッケは、私がもっとも好きな指揮者の一人であるクライバーに対して、以下のように評しています。
「彼は私にとって我慢のならない指揮者だ。彼のきちがいじみたテンポでは音楽的な体験などできはしない。
クライバーは神聖な響きの脇をすり抜けてゆく。これは悲劇だ。彼は音楽とはなにか、一度も体験したことはない」
チェリビダッケの言葉は辛辣で過激ですが、とても面白く、的を射ているところもあると思います。
「トスカニーニは楽譜通りに演奏した唯一の指揮者だといわれてきた。といっても、彼はそもそも音楽など響かせず、音符だけを鳴らした唯一の指揮者だった。彼は純粋な音符工場だった」
(カラヤンについては、)
「彼は天才ではない。すべての若い音楽家にとってひどい毒となる実例である」
「彼は大衆を夢中にさせているやり方を知っている、コカコーラも然り」・・・・
私にとっては、チェリビダッケもクライバーも甲乙つけがたい天才音楽家、名指揮者です。両者の来日コンサートの大半に出かけており、両者の音楽が今も耳に残っています。
抽象的な表現になってしまいますが、チェリビダッケの音楽からは、世界もあらゆる存在も、“全体として一つの響き”であったことに目覚めることができますし、クライバーの音楽からは、あらゆる個々の響きが、この上ない“個性の輝き”というか、とてつもない“愛おしさ”に満ちていることを強烈に気づかせてくれます。
まったく相反するタイプの指揮者・音楽家・芸術家・人間であることだけは明白です。
チェリビダッケが、クライバーが好んだ“こうもり”や“椿姫”を振ることなど想像できず、また、クライバーが、チェリビダッケの自家薬籠中だったブルックナーなど、振るはずもなかったでしょう。(笑)
人間の心には、常に「知性と感情という天秤」が備わっており、これの用い方には私たち自身のパーソナリティ(自己観・価値観・経験則)が深く、密接に関係し、ある種の“慣性の法則”として働いています。
また、音感や聴覚といった身体的能力も一人ひとり異なっているはずですし、情意的感性に至っては、まさに一人ひとり千差万別でしょう。
したがって、厳密にいうならば、誰もが、純粋に、素直に音楽を楽しむことなどはありえず、個々の演奏家、個々の聴き手に共通の一つの音楽とは、単に物理的な空気の振動による音でしかなく、そこから先は、自分の世界を体験しているにすぎないといえます。
音楽には限りない多様性がある、演奏者にも、聴き手にも、避けがたい原型的なタイプのようなものから始まり、その場その場のあらゆる状況を含んだ一期一会として音楽は生まれ、作用しています。
さて、こんな長い前置きの後に、横山幸雄先生の美竹清花さろんでの第2回演奏会の感想、報告です。
今回は「横山幸雄が紡ぐ 編曲作品特集」というテーマで、採り上げられた曲は以下でした。
<プログラム>
バッハ(ヘス、横山幸雄):主よ、人の望みの喜びよ
バッハ=ブゾーニ:シャコンヌ
横山幸雄:オマージュ・ア・ラフマニノフ~ヴォカリーズ
ラヴェル:クープランの墓より プレリュード、フォルラーヌ、 メヌエット、リゴードン
リスト:愛の夢
リスト:リゴレットパラフレーズ
(アンコール)バッハ=グノー=横山幸雄:アヴェマリア
すべて有名な、親しみやすい曲ばかりです。ところどころに横山先生のアレンジが加えられているということですが、それがとても自然で、事前に下調べなどしていないせいもありますが、2~3カ所を除き、ほとんど気がつきませんでした。
個々の曲の内容については割愛させていただきますが、毎回新たな発見のある正鵠を射た解説、そして演奏というスタイルで、いやが上にも演奏に集中せざるを得ませんでした。
ただし、オマージュ・ア・ラフマニノフ〜ヴォカリーズ
これは横山幸雄オリジナル編曲の白眉といってもよいかも知れません。
圧巻の横山幸雄ワールドです!
響きも実に多彩で、このピアノがこんな風に鳴るのか…と言わんばかりの圧倒的な演奏でした。
ラフマニノフの美しい旋律が走馬灯のように駆け巡り、胸の奥がじんわりと熱くなる感覚を味わいました。
もちろん、同様の「バッハ=グノー=横山幸雄:アヴェマリア」も優しさが香ってくるような、それでいてバッハ、グノーの偉大さが感じられるような、すばらしい演奏でした。
横山幸雄先生のコンサートを体験していて、前置きとして長々と書いたようなことがどうでもよく吹っ飛んでしまうような迫力を感じましたが、その正体はいったいなんだろう?という疑問も頭から離れないまま終わりました。
あくまでも、ピアノにも音楽にも門外漢だからこそ、大胆に言うことができるのですが、
やはりホンモノの演奏というものは、全体の構成が一つの統一体となっていて、訴えている主題が途切れることなく明確に感じられ、さらに個々の音すべてが意味をもった音楽となって響いており、無機的な音も沈黙もないこと、意識を内面に向けさせ、瞑想に誘うもの――
そんなふうにいえるのではないかと感じました。
毎回、感心させられてしまう横山先生の演奏は、まさに最初の一音から、最後の一音が消えるまで、全体としても、個々としても、音楽がみなぎっていて、途切れることなく響き続けます。
その域に達していない演奏というものは、部分的に何がしたいのか、どう弾きたいのかが曖昧になってしまったり、不明になっている箇所が多かったり、不自然さがあったり、無機的な音や沈黙が、ホンモノの音楽(響き)とそうでない音楽(響き)とが、ゴマ塩のように混ざっているように感じられたりします。
横山先生の演奏は、どんな曲でも颯爽としており、無駄な淀みや弛みがありません。
今回の「横山幸雄が紡ぐ 編曲作品特集」では、最初の「バッハ(ヘス、横山幸雄):主よ、人の望みの喜びよ」から、アンコールの「バッハ=グノー=横山幸雄:アヴェマリア」にいたるまで、こんなに完成度の高い演奏を、このような些細な少人数のサロンで贅沢に聴くことができるということに、もったいないという想いを何度も味わいました。
(渡辺公夫)