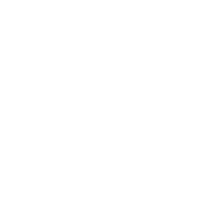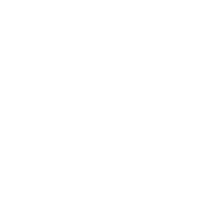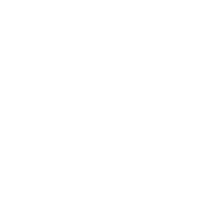こちらは絵画の個展のような形で菱田麻耶「展」という形で開催させていただきました。
菱田さんは共感覚者であり、人のオーラや音が色で見えるそうで、一言でいうと、とっても”心が綺麗”な方です。
作品も現代音楽独特の聞きにくさがなく、不思議とすんなりと包み込むように入ってくるようでした。
当日は満員御礼で大変熱気に包まれており、大盛況となりました。

1. Prelude to Soaring(Soprano:菱田麻耶、Piano:比果沙織)
明確な輪郭のない、水を思わせるピアノに乗って、歌詞を持たないソプラノがあてどなく彷徨いながら始まりました。
形を持たないものの、ピアノに時折、日本的な音響が垣間見え、どこか懐かしさを感じて曲に引き込まれていきます。
共感覚を持つ作曲者は、この曲に「青」を感じるようです。たしかに、澄んだ響きが会場に清澄な空気を誘い込み、空気を青色で満たしていくように感じられました。
中音域をたゆたっていたソプラノも、高音域へ抜けると解き放たれるように自由に舞い始めます。これが、Soaring 飛翔、の感覚なのでしょう。

2. Scenery from Tate Modern(S.sax:井上ハルカ、小鼓:望月太喜之丞)
クリアで混じり気のない楽音を奏でる安定した楽器であるサックスと、ほとんどが噪音であり微細な音程の変化と空間が魅力的な繊細な楽器である小鼓…これほど、その魅力の性質が対極にある楽器の組み合わせはないでしょう。
さらに、ソプラノサックスは現代奏法も駆使し、古典的な奏法の小鼓の余韻に割り込んでいきます。ソプラノサックスの圧倒的優位に見えていましたが、しばらく聴いていると…どうでしょう、小鼓は大きな懐の大きさを持ち、少しも動じません。やがて、リズミカルな楽想に到達すると、無邪気に飛び跳ねるサックスの旋律の裏拍にうまく小鼓がかみ合い、両者が音楽の中で自由に共存し始めます。どちらも迎合することなく、自我を保ちながらもお互いを受け入れるのです。
作曲者のプログラムノートによると、 高層建築物とセント・ポール大聖堂などの歴史的建造物が共存するロンドンの金融街の風景にインスピレーションを受けた、とのことでした。新旧の融合が、音楽で見事に表現されていました。

3. 大熊座伝説(Piano:入川 舜)
⑴大熊座と小熊座
美しい音が散りばめられ、夜空に瞬く星が目に浮かぶような曲ですが、ただ美しいだけではなく、「何かある」と感じさせる不思議な響きも隠し味のように仕込まれていました。
仲良くキラキラと輝く大熊座と小熊座の、美しくも悲しい波乱に満ちた物語が紐解かれていきます…。
⑵月
柔らかい月の光を思わせる優しい和音の上で、無垢で澄んだ輝きを持つ旋律が優雅に遊ぶ。月の女神アルテミスと、その従者であり、のちに大熊座に姿を変えられたニンフ、カリストの描写なのでしょう。穢れを知らない純粋な響きに、次第に前曲で聴かれた不気味な和音が混じってきます。それは、美しいカリストに恋慕するゼウスが忍び寄る影なのでしょうか。さらに、その愛によってゼウスの妻ヘラの嫉妬を買う悲劇の示唆でしょうか。
美しく透明な響きは次第に甘い色を帯び、カリストがゼウスの子を宿したことが示唆されるが、曲の最後は濁った和音が飽和して終わります。ヘラの嫉妬により雌熊に姿を変えられたカリストの咆哮でしょうか、もしくはヘラの底知れない嫉妬そのものでしょうか。
⑶アルカス
これまでの雰囲気とは一転、リズミカルで元気な楽想が登場し、舞うような旋律はなりを潜めます。カリストとゼウスの間に生まれた子、アルカスの描写でしょう。左手の毅然としたバスや、頼もしい和音などから、アルカスが立派な青年に成長したことが窺い知れます。ところが、前曲までの不穏な和音が混じりだし、トレモロで増殖し始め、曲は悲劇の響きに乗っ取られます…アルカスは森で母である雌熊を、そうとは知らずに射殺そうとしてしまうのです。緊張が高まったところで、ふっと音が消え、疑問符のような音粒を残して終わりました。きっと、アルカス自身は自覚する間もなかったのでしょう。この様子を天から見たゼウスはアルカスも子熊に変え、親子を星座にしたのでした。
⑷ゼウスとヘラ
不快な和音がいきなり私たちにぶつかってきます。これこそ、攻撃性の高いヘラの嫉妬の響き!全曲通して影を落とし続けた和音の正体が今、やっと顕在化しました。この伝説において、一番悲しい人物はきっとヘラだったのでしょう…熊に変えられたカリストとアルカスではなく。この組曲の真の主人公もまた、ヘラであるような気がしてなりませんでした。
自制できない嫉妬に飲み込まれていくように、怒りのトレモロが沸き上がり、不協和音が放り出された瞬間の迫力!そして、鍵盤から手を離し、ダンパーペダルも全開放し、響きが空気に混じっていく時の、凄まじいうねり!!ぐわん、ぐわんと、響きが波打ちました。
醜い感情をさらけ出したヘラ心が、その後さめざめと泣くような嘆きの楽想は、限りない美しさでした。なぜここまで怒ってしまうのだろう、嫉妬したくて嫉妬しているのではないのに、とでも言うような…。
最後になりましたが、この壮大で奥の深い作品を丁寧に弾き込み、無垢なカリストの音はひたすら清廉なクリアな響きで奏し、月アルテミスの温かさや息子アルカスの溌溂さ、さらにヘラを象徴する不快な音響を限りなく醜く弾き分け、作品の魅力を最大限に引き出したピアニスト、入川舜さんの繊細なタッチと超絶技巧に、絶賛の拍手をお送りさせていただきます。


4. Friendship forever(S.sax:井上ハルカ、Piano:比果沙織)
邦題は「永遠の友情」で、作曲者菱田さんの友人、中西絵莉子さんに捧げられています。
菱田さんの色彩と音の共感覚はまさに、天からの賜り物だと、そしてその作品を享受できる私たちの幸せを感じた1曲でした。この音楽は絵画のように色彩豊かに書かれており、さらに描かれた人物がじゃれ合ったり泣いたり笑ったり…と、立体的に動く不思議な絵のようです。
耳に心地好いメロディーはあるのですが、旋律が私たちの心に残すのは色彩です。ピアノの音彩とサックスの旋律の軌跡が記憶の中で混じり合い、とても美しく懐かしい、暖かい色合いを感じることができました。

5. Rhapsody(小鼓:望月太喜之丞)
この曲の色彩は「グレー」であり、音楽の元始を追求したとのトークがありました。真ん中で妖精が踊り、そのまわりをたくさんの妖精が踊り、そして狂乱度合いを増して高潮する、と…。
小鼓は紐を握ると筒に張られた皮の緊張が増して音が高くなり、紐を離すと皮が緩んで音が低くなります。このような性質を使い、小鼓を打ちながら紐を握ると「ポン?」と余韻の語尾が上がり、逆に打った後に紐を握った手を開くと「ポン↓」と決然とした表情が生まれます。また、小鼓の筒の端を打つ「タ」や「チ」という、硬めの音色で高い音を出す奏法もあります。このように、たったひとつの小鼓から生まれる多彩な音色を駆使し、掛け声も効果的に組み合わせ、さながら水墨画のような繊細かつ大胆な表現は、まさに圧巻の一言でした。

6. Paradise Lost(A.sax:井上ハルカ、Piano:入川 舜)
プログラムノートには、アダムとエバが楽園を追放されるエピソードが書かれており、「蛇の誘惑をアルト・サクソフォン、女(エバ)をピアノで表現した」とあります。
まどろむようなピアノ(エバ)は、アルトサックス(蛇)の旋律を模倣し、蛇の賢さとエバの従順さを表現しているように聴こえてきます。
蛇の誘惑に負けて禁断の果実を食べたエバが自我を得てきたかのように、どんどんピアノ(エバ)の音が明瞭になり、クライマックスを迎えます。
その後、罪悪感に襲われたのでしょうか、嘆くような切ない独白のあと、バスのリズムが生気を取り戻していきます。
そして再びクライマックスへ上り詰めていきます…これは自我の爆発でしょうか、それとも神の怒りでしょうか。
最後は、アダムとエバが追放された楽園からひとつ色彩が減ってしまったかのような、寂しさを漂わせて消えていきました。
作曲者は描写的に書いたのではないかもしれませんが、表情豊かに喋りかけてくるような音から、神話のシーンの空想が広がり、まるで劇を見るかのように聴きました。
さて、ところで、男(アダム)は?
ピアノがエバで、アルトサックスが蛇ならば、アダムはどこにいるのでしょうか。
筆者は、アダムは私たち(聴衆)だと思いました。アルトサックス(蛇)がピアノ(エバ)を誘惑し、そしてピアノ(エバ)が私たち(アダム)を誘惑する…。

会場全体が舞台となったような不思議な一体感があり、異次元の体験を出来た1日でした。
スクリャービンやメシアンも共感覚を持つ作曲家として有名です。
そんな彼らと同様、菱田さんが持つ類まれな才能に触れることができたのは貴重な機会でした。
今日生まれたこの現代音楽も、いつかはクラシック音楽の歴史を刻むことになる…
そう思うと、一見とっつきにくい”現代音楽”ですが、大切にしていきたいと考えさせられました。
(2018年7月7日開催)