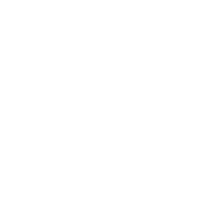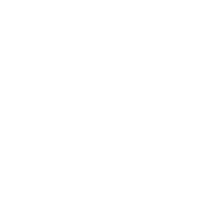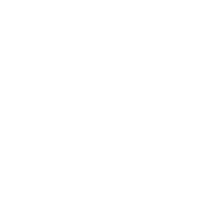“静けさを聴く”というコンセプトのもとに、20世紀前後の曲で組まれたプログラムの由来を、實川さんはこう語りました。
また、實川さんは「演奏家の没個性化」も問題視されており、今回の演奏会は彼の芸術家としての挑戦が感じられました。「静寂」と「現代音楽」、どちらもクラシック音楽界の演奏会の在り方や価値観に真っ向から挑むコンセプトですね。
このようにマニアックな内容にも関わらず、3日で満員御礼となり、急きょ、追加公演(同日開催…昼公演/夜公演)を用意せざるを得ないほどの注目と人気を集めました!

實川さんは、その先鋭な思想とは裏腹に、柔らかく穏やかな語り口で、聴き手に寄り添いながらコンサートを進めました。
コンサートの入り口となったのは、ドビュッシーの《パゴダ》(1903)。この作品の東洋的な響きは、五音音階が使われていることに由来することなど、MCで丁寧に紐解きました。
続いて、E.サティの《4つのオジーヴ》より(1886)。オジーヴとは教会のドームの補強部品のことです。
教会の雰囲気を湛えた音によって、サロン全体が中世のコラールやオルガン風の響きに満たされます。音量そのものは大きいのですが、そのベクトルが内省的なため、私たちのなかに静かなものとして染み入ってきます。
そして、J.ケージのピアノ作品へ。「ケージといえば、『休符も音楽なのだから、休符ばかりを集めても音楽になる』と、《4’33”》を書いた作曲家として有名です」とケージを紹介し、ケージの静寂に対する意識の高さに共感を示しました。実際に弾かれたのは、《ある風景の中で》(1948)。
實川さんは、「ある風景、と言い方をぼかしているのは、聴き手の想像力を規定しないためだと思います」と述べ、曲の解釈を最小限にとどめて弾き始め、弾き終わったあとに、「この曲の風景は自分のなかではモノクロで、人気がなく荒廃していて、幸せではない場所のように感じます」と、ご自身のイメージを述べました。
対して、武満徹の《ロマンス》(1948)については、楽譜に“nobile e funebre(気品をもって悲しく)”とあることから「funebreにはお葬式という意味もあり、モノクロの葬列が思い浮かびます」とのこと。
《ある風景の中で》と《ロマンス》に共通するモノクロの世界観が、作曲家の国境を越えて私たちに迫りました。
前半の最後は、再びドビュッシーに戻って《沈める寺》(1910)を。
神秘的な寺と鐘の音が、前半のプログラムの東洋的なものと宗教的なものを包み込んで迎え入れるような、懐の深さを感じる演奏でした。

後半は、またコンサートの冒頭にトリップして戻ったかのように、ドビュッシーの《グラナダの夕べ》(1903)から始まり、その先は時代をどんどんと下り、現代につながっていきます。
まずは、演奏会で採りあげられることが大変珍しい作曲家であるシェルシの、《第8組曲“Bot ba”》より(1952) 。
これはチベットの寺院の様子をイメージして作曲されたもので、實川さんはこの曲の曲想について「普段から抑揚の激しいイタリア語を喋っているシェルシからは、東洋のお経は抑揚がなさすぎて、人間味がなく、気味が悪く感じられたのでは。日本人からしても、お経は普段の話し言葉とは全然違いますが、安らぎを感じる人が多いと思います。実際には、チベットの寺院はこんなに不気味ではなかったと思います」と解釈し、曲そのものが持つ底知れなさを表現しつつも、必要以上に不気味さを強調せず、淡々と演奏されました。
西洋人から見た東洋の曲ともいえる、この《第8組曲“Bot ba”》を懸け橋として、邦人の作品へと、プログラムが移り変わります。まずは矢代秋雄の《夢の舟》(1960)。原曲は連弾用ですが、ソロ用に編曲されたものが演奏されました。ほっとする優しい小品でした。

そして、西村朗の《星の鏡》(1992)では、夜公演において“照明を全消しする”という新たな試みが行われました!
ソステヌートペダル(真ん中のペダル)を使って倍音の共鳴を利用した残響を伴う奏法、實川さんの硬質で純度が高い音色…、不思議な響きと透明な音が、真っ暗なサロンにきらきらと降りそそぎ、まるで宇宙空間と星屑のきらめきのようでした。
プラネタリウムにいるかのような、全身で音を浴びて音楽を享受する、まさに五感で感じる演奏でした。
体が浄化されるような、不思議な空間が生み出されました!

最後の曲は、平井京子の大作、《3つのアリオーソ》(2011)でした。この曲は實川さんご自身が初演を行ったそうで、演奏会で弾くのは今回が三度目だそうです。
夜公演には、作曲者の平井さんご自身が聴きに来られました。
この曲は東日本大震災をうけて書かれた作品で、實川さんは当時の状況を「震災後、自粛モードの漂うなか、皆さんお仕事されていたと思いますが、われわれ演奏家や劇場関係者は、一か月間は完全に公演が中止され、仕事が全くありませんでした。こういう時、音楽は無力だと、ひしひしと感じました」と語り、「1曲目は重い気持ち、2曲目は《桜2011》という副題があり、震災後に咲いていた桜がモチーフになっているそうです。3曲目は前向きな気持ちです」と曲の説明をして、演奏に入りました。
1曲目は、淀む曲調のなかに、突然、崩れていく音型がところどころに現れます。
当たり前だった日常が脆く崩れてしまう危うさや、災害の大きな力の前になす術を持たない自分の無力感、ゆるやかな絶望が、実感をともなって音へと立ち上がり、言い表しようのない淀んだ思念がサロンの空間に充満していきます。
2曲目は退廃的であり閉塞感のある思念の塊を、はらはらと舞い落ちる桜の花びらの動きの音型が、少しずつ、少しずつ、解きほぐしていきます。
灰色の音色と、桜のコントラストがあまりに美しいために、思わず涙がこぼれそうになりました。そのとき、花びらが舞い落ちるさまと、涙が頬を伝う軌跡が、とても似ていることに気付きました。
3曲目は「前向き」との説明でしたが、一般的にポジティブさを表すはつらつとした曲想ではないようです。
己の無力を受け入れ、絶望をかみしめた上で、達観し、自分にできることからひとつずつ取り組み、一歩一歩進んでいく…、そんな静かな決意を感じさせる演奏でした。
ここに、力強い“静寂”がありました。

アンコールは、1曲目は両公演ともに、ドビュッシーに立ち返って《ヒースの茂る荒地》、2曲目は、昼公演ではさらに時代を遡ってシューマンの《トロイメライ》が弾かれました。
夜公演での2曲目は、趣向を変えつつも、今回の隠れテーマともいえる“東洋”が思想のベースなのでしょうか、
日本の歌を實川さんにがジャズ風にアレンジした、見事な即興演奏が披露され、實川風というピアニストの類い稀な才能感じる公演となりました!
反響も大変大きく、来年のシリーズ化に向けて企画の方も進めて参ります。
(2018年10月20日開催)